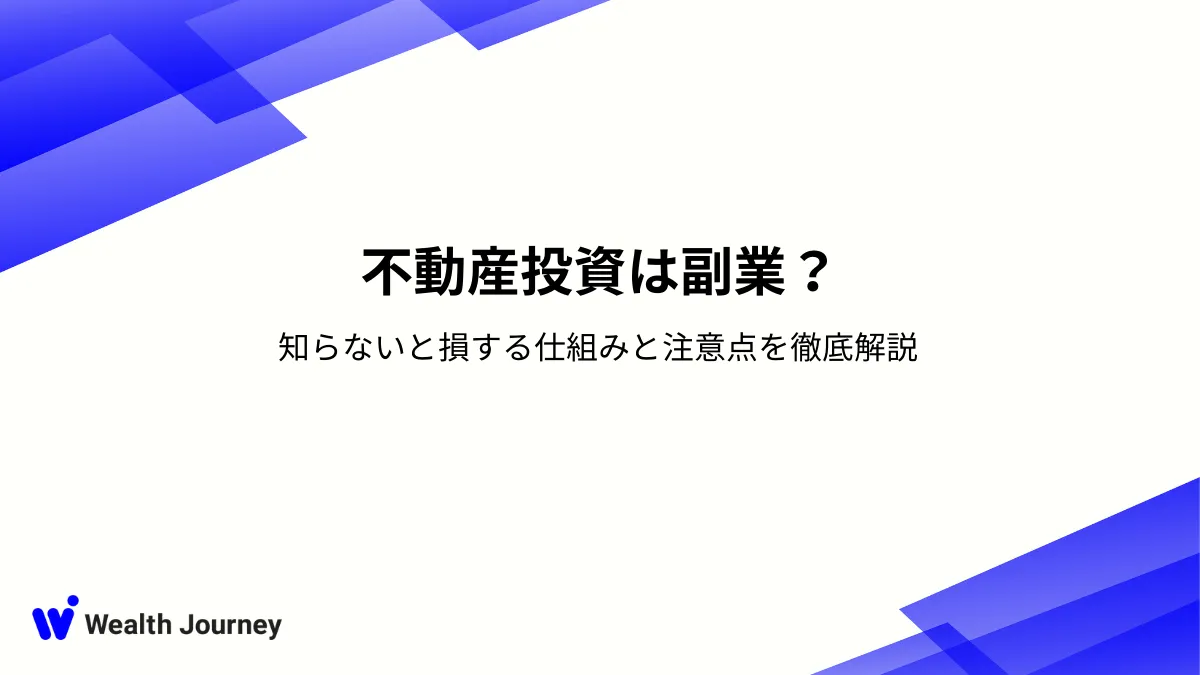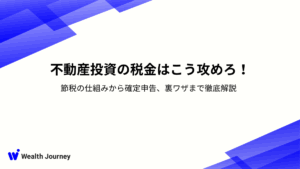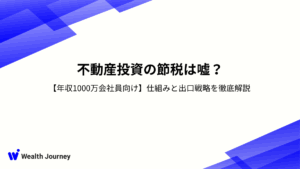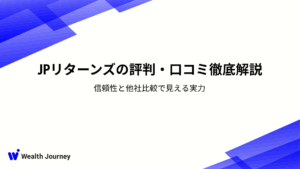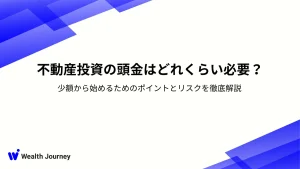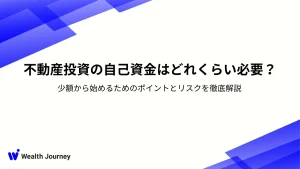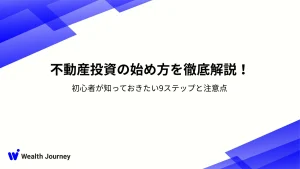会社や公務員として働きながら不動産投資を始めたい、もしくは既に物件を所有しているけれど、副業として見なされるリスクを知りたいという方も多いのではないでしょうか。結論から言うと、多くの場合、不動産投資は副業とみなされない可能性が高いです。しかし、物件数が増えたり事業的規模となる場合は、副業扱いとなるケースがあります。また、就業規則や確定申告など気をつけるポイントもいくつかあります。そこで本記事では、不動産投資が副業とみなされるかどうかのポイントや注意点、そして会社員が得られるメリットを整理して解説します。
不動産投資は副業とは見なされない可能性が高い
不動産投資は、株式投資や投資信託などと同様に資産運用の側面が強いと考えられています。実際に投資用物件を購入して家賃収入を得る行為は、労働による収益ではなくインカムゲイン(資産からの利益)として見なされることが多いため、一般的には「副業」扱いにはならないケースが多いのです。
ただし、会社員として働いている場合でも、複数の物件を所有し大規模に経営を行っていると、副業や事業として見なされる可能性があります。会社や職種によっては副業が規定で禁止されていることもあるため、事前に就業規則を確認し、自身の運用スタイルがどの程度の規模にあたるか把握することが重要です。
不動産投資が副業とみなされない理由4つ
以下では、不動産投資が副業に当たりづらいと考えられている4つの理由について解説します。
| 理由 | 説明 |
|---|---|
| 資産運用としてみなされるため | 労働による収益ではなく、資産運用から得られる利益とされるため、本業とは別扱いとなり、副業に該当しないケースがある。 |
| 相続や譲渡などにより不動産運用を行うケースがあるため | 相続や譲渡によって不動産を所有・管理している場合は、「副業を始めた」とはみなされず、副業とは切り離されて考えられる。 |
| 本業に支障が出づらいため | 管理会社に委託することで労力が少なく、自主管理しない限り日常的な負担が軽いため、本業への支障が少ない。 |
| 情報漏洩リスクが低いため | 会社業務と直接関係がないため、情報漏洩などのリスクが少なく、副業としての制限を受けにくい。 |
資産運用としてみなされるため
不動産投資は株式投資や投資信託と同様に、労働対価ではなく「資産を運用して得られる利益」とみなされることが多いです。そのため、本業で働く時間を割かずに収益を得られる点から、会社の就業規則に触れず、副業に該当しないとされるケースがあります。
相続や譲渡などにより不動産運用を行うケースがあるため
親族から相続を受けて物件を所有している場合や、譲渡により管理を任されているケースも考えられます。こうした状況では、本人が積極的に「副業を始めた」というよりも、所有している不動産をそのまま運用している状態と解釈されるため、副業とは切り離して考えられることがあります。
本業に支障が出づらいため
労働集約的な業務が少なく、基本的には管理会社へ委託すれば大きな労力はかかりません。自主管理をしない限り、日常的に多くの時間を割かずに済むため、会社の就業規則上「本業に支障をきたす」という理由から禁止されるリスクが低いのです。
情報漏洩リスクが低いため
会社の業務上で得た情報を競合他社に漏らすなどのリスクが副業では問題視されます。しかし、不動産投資は自社情報との直接的な関係が薄い投資手法です。情報漏洩につながるリスクが極めて低いため、副業として規制される可能性は比較的低いと言えます。
事業的規模で不動産投資を行う場合は副業扱いとなる可能性がある
一方、不動産投資が「事業的規模」と認定されるほど物件数が多い場合は、副業や事業経営と見なされる可能性があります。一般的に、戸建てで5棟以上、もしくはアパート・マンションなどで10室以上の運用を行うと事業的規模とみなされるとされています。
以下の表でイメージをつかんでみましょう。
| 運用形態 | 規模の目安 | 副業として見なされる可能性 |
|---|---|---|
| 小規模投資 | 戸建て4棟以下、または10室未満 | 低い |
| 事業的規模 | 戸建て5棟以上、または10室以上 | 高い |
ここで注意したいのは、必ずしも上記の棟数・室数を越えたら即副業と判断されるわけではありません。就業規則の規定や実際の業務への影響、そして税務上の扱いなど総合的に判断されることが多いです。物件数を増やす場合は、事前に確認しておきましょう。
金融機関や公務員勤務の人は要注意!
勤務先の業種・業態によっては、不動産投資が厳しく制限されているケースがあります。特に、金融機関や公務員の場合は社内規定や法律で制限を受けやすい点に注意が必要です。
金融機関勤務の場合
金融機関は顧客のお金を取り扱うため、信用力が重視される業界です。そのため、従業員が不動産投資に関連して大きなトラブルや債務不履行を起こすリスクを避けようとする傾向があります。また、融資条件にも影響が出る可能性があり、金融機関勤務者が投資用不動産に融資を申し込む際は、社内規定上制限がかかる場合もあるので注意しましょう。
公務員の場合
公務員には国家公務員法や地方公務員法などが適用されるため、原則として営利企業を営むことが禁止されます。ただし、不動産投資に関しては「資産運用」として扱われる場合が多く、規模が小さいうちは問題にならないこともあります。一方、事業的規模になり「営利企業の経営」とみなされると、明確な違反となる可能性があります。公務員の場合は必ず所属機関の規定を確認し、必要に応じて許可申請を行うようにしましょう。
不動産投資を行う際に注意すべきこと3つ
副業で不動産投資を始めるリスクを回避するためにも、以下の3つのポイントをしっかり押さえておきましょう。
| ポイント | 説明 |
|---|---|
| 就業規則で不動産投資が禁止されていないか確認する | 所属企業の就業規則を確認し、不動産投資やその規模に制限がないかをチェック。違反すると懲戒処分などのリスクがある。 |
| 不動産投資の所得が20万円を超える場合は確定申告を行う | 給与以外の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要。正確な申告を怠ると、追徴課税などのペナルティを受ける可能性がある。 |
| 管理会社に物件の管理を委託する | 副業リスクを減らすために、管理業務を管理会社に委託するのが有効。手間を減らせるが、経費の見積もりも重要。 |
就業規則で不動産投資が禁止されていないか確認する
まず最初に、自分が所属する会社や組織の就業規則をチェックしましょう。不動産投資そのものが禁止されていないか、あるいは事業的規模での投資が制限されていないかを確認する必要があります。違反した場合は、懲戒処分など大きなリスクを負う可能性もあります。
不動産投資の所得が20万円を超える場合は確定申告を行う
会社員や公務員の場合、給与以外の所得が年間20万円を超えると確定申告の義務があります。不動産投資による家賃収入が安定してきたら、経費なども含めて所得をしっかり計算し、早めに税務処理を行うようにしましょう。正しく申告しないと、追徴課税などのペナルティが科される恐れがあります。
管理会社に物件の管理を委託する
不動産投資で副業リスクを最小限に抑えるためには、管理会社に物件の運営を委託するのがおすすめです。入居者募集や家賃の集金、クレーム対応などを代行してもらえるため、本業を圧迫することなく安定した運用が期待できます。ただし、管理委託料や修繕費などの経費も発生するため、シミュレーションをしっかり行いましょう。
会社員が副業で不動産投資を始めるメリット
不動産投資には、本業以外の収入を得られるだけでなく、さまざまなメリットがあります。ここでは代表的な3つのメリットを紹介します。
| メリット | 説明 |
|---|---|
| 減税につながる可能性がある | ローン利息や管理費、修繕費、減価償却費を経費として計上することで、所得税や住民税の軽減が見込める。 |
| 生命保険として機能する | 団体信用生命保険により、債務者が死亡した際にローン残債が免除され、不動産を家族に残せる。 |
| 金融機関からの資金調達がしやすい | 会社員の安定収入が信用力として評価され、自営業者などに比べて融資を受けやすく、大きな |
減税につながる可能性がある
ローンの支払利息や管理費、修繕費、減価償却費などを経費として計上できるため、結果的に所得税や住民税が軽減されるケースがあります。特に初期のうちはローン返済や減価償却の影響も大きいので、しっかり経費計上して節税を図りましょう。
生命保険として機能する
ローンを組む際に団体信用生命保険に加入すると、債務者に万一のことがあった場合にローン残債が免除される仕組みがあります。残された家族に資産としての不動産を残せることから、実質的に生命保険代わりとなる点も大きな魅力です。
金融機関からの資金調達がしやすい
会社員は安定収入があるため、一定の信用力が評価されます。自営業者やフリーランスに比べて、融資を受けやすい場合が多いのもメリットです。購入時の自己資金を抑えられる可能性が高く、より規模の大きい投資にも挑戦しやすくなります。
まとめ
不動産投資の副業は多くの場合は資産運用として扱われるため、副業規制に抵触しづらいという特徴があります。しかし、事業的規模になれば副業扱いとなる可能性もあり、就業規則に違反するリスクが生じることも忘れてはなりません。
特に金融機関や公務員の方は、所属先の規定が厳しいケースも多いため、事前の確認が必須です。確定申告を正しく行い、管理を専門家に委託するなどの対策をしっかり講じることで、本業を疎かにせず安定した収益を目指せます。
会社員として働きつつ不動産投資を行えば、節税や生命保険としての効果など数多くのメリットも得られます。将来の資産形成やリスクヘッジの手段として、ぜひ前向きに検討してみてください。